細菌検査・感染管理部門
感染症を起こす病原微生物にはインフルエンザなどのウイルス、細菌、真菌(カビ類)、マラリアなどの寄生虫など多くの種類があります。その目に見えない病原体を見つけ出し、治療のためにどの薬が効くか調べるのが細菌検査の役割です。いわゆる「院内感染の見張り番」ですが、病院内にとどまらず地域の流行の情報収集と解析を行い、感染症の治療に役立てています。細菌検査室の仕事は大きく2つに分けることができます。
細菌検査(業務委託)
感染症などの原因となる細菌や真菌、ウイルスなどの病原微生物を尿、喀痰、便、血液などの検査材料から見つけ出す検査です。病原菌を突きとめ、有効な薬剤を決めるために薬剤感受性検査を行います。また、インフルエンザウイルスなど一部のウイルスや細菌は、迅速検査と呼ばれる簡易キットを使った検査で見つけ出すことができます。

院内感染対策・PCR検査
病院内で検出される細菌、特に薬剤耐性菌と呼ばれる有効な治療薬が限られてくる細菌の院内感染対策や、感染制御チーム(ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の一員として、全職員を対象とした感染対策研修会などをはじめ、微生物ラウンド、病棟ラウンドなどに参加しています。院内に限らず京都府の新型コロナやインフルエンザなどの検出情報の収集も実施しています。

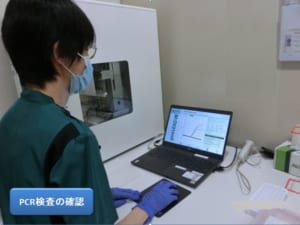
令和2年8月からは、新型コロナウイルス(COVID-19)の検出を目的としたPCR検査を院内で開始しました。それまで行政検査や外注検査では2~3日必要だった検査時間を当日中(最短3時間)に短縮し、12月以降は休日・祝日も実施し、ベッドコントロールに貢献しています。令和3年4月からは、緊急手術や緊急入院を対象とする緊急PCR検査(約60分で結果が判明)の24時間実施を開始しました。並行してコロナウイルスの変異株解析について、大学の研究機関と共同研究を実施しています。

